物語の語り手は、ジェローム。彼は、2歳年上の従姉アリサに惹かれているのだけど、アリサは母親の不倫に悩まされ、それ以来キリスト教を信じ、幸せを軽快しているためなかなかジェロームのもとにはきません。アリサは幸福ではなく、幸福へ到る道を求めていたのです。二人は惹かれ合うのですが、両者とも相手に聖なる部分を見出し、それが故に惹かれあっているので、結局結ばれることはなく・・・
恋愛小説。
「狭き門」とはマタイ福音書第7章第13節にあらわれる言葉だそうです。他の書物から引用された文章が頻出します。しかし、難しくはありません。余分なものが削りとられた写実的な描写と、平易な文体が良いです。
二人の関係は非常に歯痒いのだけれど、それがこの物語の肝になっています。
アリサは世俗的な愛を拒もうとします。そして、ジェロームのことを愛していないわけではないのに逃れていこうとします。ジェロームはそういう状態を好まず、追いすがろうとします。つまり、結婚を迫ろうとするわけです。だけど、上手に切り出すことが出来ません。
アリサの矛盾が、ジェロームを苦しめているかのようです。だけど、彼の行動が、アリサのそういう態度を誘発しているようにも感じられます。どちらかに問題があるわけではなく、両者の関係というか組み合わせに、問題があるのではないか、と感じます。
なんというか、やるせないです。
多分、二人の関係は、どうしたってうまくいくはずがないのです。アリサは、もしも幸福(結婚)になったら、あとは不幸(配偶者の死を恐れ、不倫を疑うようになる)になるしかない、といふうに感じ取ってしまう人なわけだから。
読んだ本
アンドレ・ジッド『狭き門』
読んでいる最中
遠藤周作『沈黙』
PR
時間が滅茶苦茶になってしまい、すでに未来も過去も関係なくなってしまいました。そして、時間線は一方向に流れるのではなく、破裂し、自由な方向へすすみ、しかも、それらは混じりあい、絡み合っています。そして一つの世界そのものである巨大知性体が乱立し、戦闘を繰り広げています。一番最初にあるのは、手に負えないちっちゃな女の子リタに恋してしまった、この辺りで一番賢いジェイムズとその親友、僕の物語。
SF小説。
ボルヘスを意識しているのがよく分かります。非常に説明しづらいのですが、「第一部:Nearside」9章と「第二部:Farside」9章によって構成されています。バラバラです。繋がりはあるのですが、直接繋がっていない場合もあります。
最初の内は、文章ががさつ。もう少し練られている方が良かった気がします。しかし、それが良いのかも知れない、とも感じます。ヴォネガットっぽいです。
アイディアだけで物語を強引に転がしていく短編も多いのですが、みごと。どれも面白いです。
とくに、一押しは「第二部:Farside」に収録されている「Japanese」。概算で、総計で百二十億字を超えるのだという日本文字なるものについて綴られています。漢字、漢漢字、平仮名、平平仮名、平片仮名、片平仮名などによって構成されているらしいのですが、理解できません。解読できないのです。資料が増えるごとに、文字が絶え、収集がつかないのです。そしてその短編自体も実は第一次旧日本諸島調査団の持ち帰った14ページのメモ書きで・・・
巨大知性体の上位には、超越知性体がありえるのだと判明してくるところも面白いです。本当にアイディアは素晴らしいです。
読んだ本
円城塔『Self-Reference ENGINE』
読んでいる最中
アンドレ・ジッド『狭き門』
エリック・マコーマックの短編集。『隠し部屋を査察して』『断片』『パタゴニアの悲しい物語』『窓辺のエックハート』『一本脚の男たち』『海を渡ったノックス』『エドワードとジョージナ』『ジョー船長』『刈り跡』『祭り』『老人に安住の地はない』『庭園列車』『趣味』『トロツキーの一枚の写真』『ルサウォートの瞑想』『ともあれこの世の片隅で』『町の長い一日』『双子』『フーガ』収録。
奇怪な世界や現象が描かれています。
ゆがみが印象的です。たいてい隣人が登場すると狂っています。現実から遊離しているわけではないのですが、どの短編もどこか捻じ曲がっているし、奇天烈です。
地味だけど、ぞっとします。何らかの欠損や、よく分からないエロとグロが度々あらわれます。意味を見出そうとするのは徒労ではないか、と感じるほど。しかし、そういう不気味なところが面白いです。
『一本脚の男たち』
炭鉱のまわりにある村落の物語。そこには、一本脚の男たちが溢れています。そこはかれらのなわばりなのです。かつて、恐ろしい事故に襲われてから、そうなのです・・・
読んだ本
エリック・マコーマック『隠し部屋を査察して』
読んでいる最中
シオドア・スタージョン『人間以上』
星新一のショートショート。『新発明のマクラ』『試作品』『薬のききめ』『悪魔』『災難』『九官鳥作戦』『きまぐれロボット』『博士とロボット』『便利な草花』『夜の事件』『地球の皆さん』『ラッパの音』『おみやげ』『夢のお告げ』『失敗』『目薬』『リオン』『ボウシ』『金色の海草』『盗んだ書類』『薬と夢』『なぞのロボット』『へんな薬』『サーカスの秘密』『鳥の歌』『火の用心』『スピード時代』『キツツキ計画』『ユキコちゃんのしかえし』『ふしぎな放送』『ネコ』『花とひみつ』『とりひき』『へんな怪獣』『鏡のなかの犬』『あーん あーん』収録。
寓話のようなSF、なのか。
醒めています。不思議なほど、直截です。面倒な説明は省かれているので、物語をそのままに受け取らざるを得なくなります。妙なるなにかがあるわけではないのに、それが故に面白くなっています。
質の高い御伽噺、といえるのではないか。
固有名詞はほとんど使われておらず、なおかつ平易な言葉のみで構成されています。暴力、性、前衛的表現、あとは時事ネタなど、刺激的な題材はほとんど用いられていません。他の作家と同じことはしない、ということだから、ひねくれているということもできますが、星新一はモラルを大切にする人なのだと思います。鋭い文明批評も含まれています。
基本的にクール。その裏側には科学への盲信に対する反発があるのではないか、と思わないでもないのですが、過剰ではありません。非常にストイック。引き締められています。
読んだ本
星新一『きまぐれロボット』
読んでいる最中
エリック・マコーマック『隠し部屋を査察して』
『社会を生きるための教科書』は、様々なことを扱っています。働くということ、お金を扱うということ、溢れる情報とつきあっていくことなどがまとめられています。
最初はあまり興味がなかったのですが、読んでいて、とても考えさせられました。役に立ちそうなので、手元に置いておこう、と思いました。読み物として面白い、というより、こういうときどうすれば良いんだろう、と考え始めるときに必要な手がかりが幾つも用意されている教科書のような本だなぁと感じました(教科書というのは、ある世界の詳細(そんなものはまとめられないよなぁ)というよりは、その世界の見取り図と入り口までの地図がのっていれば良い気がするのだけど、それがそろっていて、とても良い気がしました)。
あるジャンルのことのみでなく、様々なことが扱われているのだけど、コンパクトで把握しやすいです。この本だけを頼りにするわけにはいかないけど、困ったとき、気軽にパラパラとめくれるところが良いなぁと感じます。
こういう本は、なんかありそうでなかなかない気がします。
読んでいて参考になりましたが、生きていくためにはいろんなことを考えないといけないのだなぁ、と考えてしまいました。なんというか、疲れないでもないです。もう少しシンプルに、素朴に生きていくことができたら良いのに。しかし、様々な制度が存在している社会の中で生きていこうとするならば、手続きや処理が複雑になるのはしかたないのか。
とくに、心に残ったのは、一番最後におかれている「ドグマを確立する」という部分でした。そうしないといけない、というのは普段から思っているのだけど、本当に難しいんだよなぁ・・・
『実験でわかるインターネット』は、インターネットの仕組みを解説したもの。しかし、手引きと言うわけではありません。基礎的な仕組みが分かりやすく解説されています。読んだからといって、何かを使えるようになるわけではないけど、考えるためには役に立ちます。
ウェブサイト、メールなど様々なものが溢れているから、なんとなく使っていました。しかし、それらが内側でどのような処理を行っているのか今まで知りませんでしたが、そういったことを知るための手がかりを得ることが出来て良かったです。まぁ、やっと玄関口にたどりついただけなのかも知れないけど。
どちらも岩波ジュニア新書の本。
読んだ本
川井龍介『社会を生きるための教科書』
岡嶋裕史『実験でわかるインターネット』
読んでいる最中
エリック・マコーマック『隠し部屋を査察して』
SFマガジン編集部『SFが読みたい! 2010年版』
稲垣足穂、小栗虫太郎、埴谷雄高といったそれなりに有名な作家から、もっとマイナーな作家までが紹介され、論じられています。読むと、かえって澁澤龍彦という人のことが分かります。選び方が、良いです。紹介されている作品を読みたくなります。
評論集。
谷崎潤一郎に関する洞察は面白いです。形而上学が欠けているといわれる谷崎潤一郎は地震に影響を受けていたのか。
稲垣足穂を「抽象志向と飛行願望、メカニズム愛好と不毛なエロティシズム、天体とオブジェ」というふうにまとめたのは澁澤龍彦だとは知りませんでした。
三島由紀夫も登場。対談などものっています。からみが面白いです。
読んだ本
澁澤龍彦『澁澤龍彦 日本作家論集成 上』
読んでいる最中
エリック・マコーマック『隠し部屋を査察して』
川井龍介『社会を生きるための教科書』
岡嶋裕史『実験でわかるインターネット』
私と、私が恋している無邪気な黒髪の乙女の物語。『夜は短し歩けよ乙女』『深海魚たち』『御都合主義者かく語りき』『魔風邪恋風邪』収録。
『夜は短し歩けよ乙女』
黒髪の乙女は、酔うと顔を舐めだす羽貫さんや、ふわふわして捉えどころのない樋口さんに出会い、誘われ、京都先斗町を闊歩。浴びるように酒を飲むのですが全く酔いません。一方、彼女を追う僕は、ずぼんを剥がされたり、酷い目にあいつつ放浪することになります・・・
『深海魚たち』
黒髪の乙女が出向いていると聞き、僕は古本市に赴きます。黒髪の乙女は「ラ・タ・タ・タム」という絵本を探しています。一方、僕は彼女が、ある本に手を差し出したとき、同時にその本に手を差しだすべく、妄想するのですが、「火鍋」という恐ろしい我慢大会に参加することになり・・・
『御都合主義者かく語りき』
学園祭が行われます。学園祭事務局長は、狂ったようにはめをはずしている人たちを追跡し、注意、あるいは逮捕してまわるのですが、「韋駄天コタツ」と「偏屈王」は捕まらず、各所でゲリラ演劇が行われ・・・
『魔風邪恋風邪』
とんでも風邪が京都を襲います。誰もが倒れていき、京都は閑散としてしまいます。それなのに、活発な黒髪の乙女だけは無事で・・・
恋愛小説。
大袈裟で、滑稽で、顰めつらしくて、引用に満ちていて、しかも愉快で、癖がある森見登美彦の文体は楽しいです。物語の舞台は、何が起こってもおかしくない京都。他の森見作品ともつながりがあります。それを探していくのも楽しいです。
物凄い登場人物たちも楽しいです。とくに、李白という人は何者なのか分からなくて面白いです。血も涙もない高利の金貸しらしく、「電車」という三階建ての巨大な自家用車を所有しているのに、良い人のようでもあって・・・
第20回山本周五郎賞受賞作。2007年第4回本屋大賞ノミネート作(2位)。
読んだ本
森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』(再読)
読んでいる最中
エリック・マコーマック『隠し部屋を査察して』
『アメリカの夜』とは、フランソワ・トリュフォーという監督がつくった映画のタイトルだけど、もともとは映画に用いられる技法のひとつなのだそうです。「一年じゅう空が晴れているカリフォルニアの昼間を、キャメラの絞りと光学フィルターの操作でフィルムにたいする露光を調節して、夜の場面として撮影してしまうハリウッド映画特有の「夜」である」と作中で説明されます。
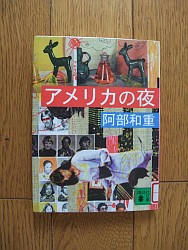
映画を扱った小説、なのか。
主人公は映画の人でした。映画を扱っている大学へいきます。しかし、その後Sホールに勤務するようになり、勤務中に『ドン・キホーテ』や『失われた時を求めて』や『神聖喜劇』を読み耽ります。ですが、彼は基本的には「映画の人」であり続けます。
そして、主人公は特別な存在になりたいと願う人たちの中でもがき続けることになります。その辺りの描写は秀逸。
特別な存在になりたい、と願う若者の滑稽な、それでいて哀しい振る舞いが綴られています。
映画に対する、倒錯的な愛が感じられます。それが良いです。映画(あるいは、文学に置き換えても構わない気がする)を熱烈に愛し、それにこだわることが、滑稽にしかなりえない今の時代に適応することができない主人公の姿が、良いです。
主人公と語り手が分裂しているところも愉快です。まどろっこしいし、青臭いけど、今となってはそうすることでしか文学に取り組めないのではないか、と感じます。80年代以降の状態に自覚的といえるのではないか。
読んだ本
阿部和重『アメリカの夜』
読んでいる最中
ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』
映画を扱った小説、なのか。
主人公は映画の人でした。映画を扱っている大学へいきます。しかし、その後Sホールに勤務するようになり、勤務中に『ドン・キホーテ』や『失われた時を求めて』や『神聖喜劇』を読み耽ります。ですが、彼は基本的には「映画の人」であり続けます。
そして、主人公は特別な存在になりたいと願う人たちの中でもがき続けることになります。その辺りの描写は秀逸。
特別な存在になりたい、と願う若者の滑稽な、それでいて哀しい振る舞いが綴られています。
映画に対する、倒錯的な愛が感じられます。それが良いです。映画(あるいは、文学に置き換えても構わない気がする)を熱烈に愛し、それにこだわることが、滑稽にしかなりえない今の時代に適応することができない主人公の姿が、良いです。
主人公と語り手が分裂しているところも愉快です。まどろっこしいし、青臭いけど、今となってはそうすることでしか文学に取り組めないのではないか、と感じます。80年代以降の状態に自覚的といえるのではないか。
読んだ本
阿部和重『アメリカの夜』
読んでいる最中
ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』
篠田一士が二十世紀の十大小説を選び、それを紹介し、論じていきます。十大小説としてあげられてるいのは、『失われた時を求めて』(プルースト)/『伝奇集』(ボルヘス)/『城』(カフカ)/『子夜』(茅盾)/『U.S.A』(ドス・パソス)/『アブサロム、アブサロム!』(フォークナー)/『百年の孤独』(ガルシア=マルケス)/『ユリシーズ』(ジョイス)/『特性のない男』(ムジール)/『夜明け前』(島崎藤村)。
非常に面白い企みではあります。著者は、最初に「タイトルを記してみて、いまさらのように、神をも畏れぬおおけなさ、というかその阿呆らしさを、つくづく思い知る。」と記しています。それでもあえて『二十世紀の十大小説』といくところが愉快です。
示唆に富んでいます。篠田一士の読みが提示されています。
いろんな地方の小説が選ばれています。『失われた時を求めて』(プルースト)はフランスの小説。『伝奇集』(ボルヘス)は『伝奇集』(ボルヘス)の小説。『城』(カフカ)はチェコで書かれたドイツ語の小説。『子夜』(茅盾)は中国の小説。『U.S.A』(ドス・パソス)と『アブサロム、アブサロム!』(フォークナー)はアメリカ合衆国の小説。『百年の孤独』(ガルシア=マルケス)はコロンビアというかラテンアメリカの小説。『ユリシーズ』(ジョイス)はアイルランドの小説。『特性のない男』(ムジール)はオーストリアの小説。『夜明け前』(島崎藤村)は日本の小説。
それらを紹介していく篠田一士の手際はみごと。
読んだ本
篠田一士『二十世紀の十大小説』
読んでいる最中
ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』
24世紀、人間はテレポーテーションを可能にしました。それは、発見者の名をとってジョウントと呼ばれています。勿論、人間の生活は激変し、バランスが崩れたため、内惑星連合と外衛星同盟の間では戦争が勃発します。25世紀、プレスタイン財閥の宇宙船ノーマッドは攻撃を受け、漂流します。唯一の生存者ガリヴァー・フォイルは近くを通った同じくプレスタイン財閥の宇宙船ヴォーガに助けを求めますが、無視され、激怒し、復讐を誓います。その後、フォイルはサーガッソ小惑星群に住む科学人のもとへたどり着きますが、顔に刺青の虎のような模様とN♂MAD1という文字を彫られてしまい・・・
1956年に発表されたSF小説。
『モンテ・クリスト伯』をモチーフにしているそうです。主人公はヴォーガに復讐するためだけに、宇宙を駆けめぐります。彼は野蛮なので、虎と呼ばれます。とはいえ、強靭だし、どのようなときでも諦めません。とにかく圧倒的なのです。
財閥を率いるプレスタインの娘、オリヴィアは印象に残ります。彼女は、普通の物は見えないのですが、赤外線などを感じられる特殊な目を持っています。純白の雪の処女などと表現されるので、いかにも、典型的なお嬢様のように思えますが、実はそうではない、と発覚します。
全体的には、八方破れになりかかっています。
破壊的。とくにラストの辺りは凄まじいです。小説というものではなくなる寸前のところにまで到達してしまいます。しかし、それが魅力。
SFの古典。後の作品に影響を与えたようです。たとえば、多くのアイディアは石ノ森章太郎に、前衛的な部分は筒井康隆に影響を与えています。読むだけで分かります。
読んだ本
アルフレッド・ベスター『虎よ、虎よ!』
読んでいる最中
篠田一士『二十世紀の十大小説』
グレッグ・イーガンの短編集『しあわせの理由』を読みおわりました。『チェルノブイリの聖母』『ボーダー・ガード』『血をわけた姉妹』『しあわせの理由』。
『チェルノブイリの聖母』
物語の舞台は近未来。探偵は、行方不明になった聖母像のイコンを探し出す仕事を請け負います。
『ボーダー・ガード』
量子力学の話。量子サッカーというものが登場。
『血をわけた姉妹』
姉妹の物語。人工的なウイルスが拡大し・・・
『しあわせの理由』
少年は、脳腫瘍のため、いつでも幸せに包まれているようになります。しかし手術すると、今度は幸せを感じることができなくなってしまい・・・
読んだ本
グレッグ・イーガン『チェルノブイリの聖母』
グレッグ・イーガン『ボーダー・ガード』
グレッグ・イーガン『血をわけた姉妹』
グレッグ・イーガン『しあわせの理由』
読んでいる最中
アルフレッド・ベスター『虎よ、虎よ!』
『チェルノブイリの聖母』
物語の舞台は近未来。探偵は、行方不明になった聖母像のイコンを探し出す仕事を請け負います。
『ボーダー・ガード』
量子力学の話。量子サッカーというものが登場。
『血をわけた姉妹』
姉妹の物語。人工的なウイルスが拡大し・・・
『しあわせの理由』
少年は、脳腫瘍のため、いつでも幸せに包まれているようになります。しかし手術すると、今度は幸せを感じることができなくなってしまい・・・
読んだ本
グレッグ・イーガン『チェルノブイリの聖母』
グレッグ・イーガン『ボーダー・ガード』
グレッグ・イーガン『血をわけた姉妹』
グレッグ・イーガン『しあわせの理由』
読んでいる最中
アルフレッド・ベスター『虎よ、虎よ!』
ポストモダンという言葉は80年代に持てはやされ、今では過去の遺物のように扱われているが、実はポストモダンが徹底化されたのは90年代なのであり、世界の断片化がすすんでいる、というのが著者の主張。そこまでは、現代思想としては当たり前なのですが、著者は、それを肯定せず、自分を媒介にして、分断されたものどうしを繋げていこうとします。そして、様々なものを論じます。たとえば、ソルジェニーツィン、多和田葉子、エヴァ、デリダ、阿部和重、柄谷行人、筒井康隆を論じていきます。
東浩紀の評論集。
綺麗に整理されています。とにかく切れ味が鋭いし、結論には説得力があります。あまりにもスパッといくので、逆に不安になるほどですが、著者はそれも自覚しているようです。
たとえば、スラヴォイ・ジジェクは便利な論法で何でも切り捨てていく、と喝破します。それを理解しているのならば不安は感じません。その辺りのバランス感覚も良いです。
ポストモダン的状況の中で島にこもるのはよくない、とあえて結論付けるところはかっこいいです。しかし、東浩紀もサブカルチャーにけんかを吹っかける振りをしつつ仲良くしている、としか思えないからなぁ・・・ 有言実行になればいいのだけど。
読んだ本
東浩紀『郵便的不安たち#』
読んでいる最中
グレッグ・イーガン『しあわせの理由』
グレッグ・イーガンの短編集『しあわせの理由』を読んでいる最中。『適切な愛』『闇の中へ』『愛撫』『道徳的ウイルス学者』『移相夢』
『適切な愛』
列車事故で重傷を負ってしまった彼氏の脳を腹中に収めた女性の物語。
『闇の中へ』
なぜか突如として出現する「吸入口」。一方向へしかすすめない不気味な空間が生まれます。反対方向へすすもうとすると死んでしまうのです。
『愛撫』
強盗に殺害された老博士の部屋からスフィンクスが発見され・・・
『道徳的ウイルス学者』
生物学者ジョン・ショウクロスは、神の意思を実現し、不倫と同性愛をセカイから排除するため、ウイルスを発明します。
『移相夢』
脳をスキャンして、機械化するためには、手術が必要で、その過程で移相夢なるものをみることになるらしく、不安になるのですが・・・ 現実が溶解していきます。
読んだ本
グレッグ・イーガン『適切な愛』
グレッグ・イーガン『闇の中へ』
グレッグ・イーガン『愛撫』
グレッグ・イーガン『道徳的ウイルス学者』
グレッグ・イーガン『移相夢』
読んでいる最中
東浩紀『郵便的不安たち#』
中篇集のような長編。『ドニヤーザード姫物語』『ペルセウス物語』『ベレロフォン物語』収録。物語が進んでいく傍から、解説されていきます。
ポストモダン文学。
なんというか凄いです。『ドニヤーザード姫物語』が下敷きにしているのは、アラビアンナイト。物語ることとセックスの関連について綴られています。それなりに分かりやすいです。語らなければ死が待っている、という構造がうまいぐあいに活かされています。男女の平等はありえるかと考察されています。
『ペルセウス物語』が下敷きにしているのは、ギリシア神話に登場する英雄ペルセウスの物語。ペルセウスはゴルゴーンを退治し、アンドロメダーと結婚した英雄です。
一方、『ベレロフォン物語』が下敷きにしているのはギリシア神話に登場する英雄ベレロフォンの物語と『ペルセウス物語』。ベレロフォンはキマイラを退治し、ペガサスに乗って天を目指し、ゼウスに殺された半英雄です。
『ベレロフォン物語』が一番長いのですが、失敗作のようです。入り組んでいるので訳が分からないのです。支離滅裂になりかかっています。そして、失敗していることこそが作品の意味である、というふうになっています。ひねくれています。
説明するのは非常に難しいです。しかし、たどっていくのは楽しいです。それに書き手が誰なのか、発覚するところはまるでミステリのよう。書かれたものである、ということが意識されているところは変な感じです。しかし、それでこそポストモダン文学なのではないか。不気味なキマイラになりうるのではないか。
読んだ本
ジョン・バース『キマイラ』
読んでいる最中
グレッグ・イーガン『しあわせの理由』
★★
作者: 高田崇史
出版社: 講談社
百人一首を深く愛していた財産家、真榊大陸が何者かに殺害されます。彼は、百人一首の中に含まれているある句を握ったまま、倒れていました。それは、多分ダイイングメッセージ。いったい何を表しているのか・・・? そもそも百人一首そのものにも、いろんな謎が隠されています。それらの謎を、博覧強記の薬剤師、桑原崇が解明していきます。
「百人一首の謎」を解明する部分は、楽しかったです。結構牽強付会のような気もします。でも、通説に対して面白い異論を唱える時はかなり強引にやらないとだめなものだし、これは研究書ではなくて、楽しむためにある小説なのだからそういうことも許されるのではないか。面白いこと考えるなぁ、というふうに受け止めました。
しかし、現実に起きた殺人事件の解明はふざけている、と僕は感じました。まるで京極夏彦。感覚は疑わしいものだ、みたいな方向に推理を進めていき、最後までそれを押し通すわけです。なんというか、脱力しました。
ようするに、事件の決着のつけ方は、京極夏彦の亜流としか思えないような感じなので僕はちょっと納得できないのですが、百人一首の謎があるおかげで全体としては楽しめました。とくに、主人公による歴史の解説が面白いです。セリフと地の文の区別がつかなくなるほど、どこまでも延々と続いていくのだけど、平安貴族のドロドロした闘いを分かりやすく説明してくれて、読まされます。
第9回メフィスト賞受賞作品。
自森人読書 QED―百人一首の呪
作者: 高田崇史
出版社: 講談社
百人一首を深く愛していた財産家、真榊大陸が何者かに殺害されます。彼は、百人一首の中に含まれているある句を握ったまま、倒れていました。それは、多分ダイイングメッセージ。いったい何を表しているのか・・・? そもそも百人一首そのものにも、いろんな謎が隠されています。それらの謎を、博覧強記の薬剤師、桑原崇が解明していきます。
「百人一首の謎」を解明する部分は、楽しかったです。結構牽強付会のような気もします。でも、通説に対して面白い異論を唱える時はかなり強引にやらないとだめなものだし、これは研究書ではなくて、楽しむためにある小説なのだからそういうことも許されるのではないか。面白いこと考えるなぁ、というふうに受け止めました。
しかし、現実に起きた殺人事件の解明はふざけている、と僕は感じました。まるで京極夏彦。感覚は疑わしいものだ、みたいな方向に推理を進めていき、最後までそれを押し通すわけです。なんというか、脱力しました。
ようするに、事件の決着のつけ方は、京極夏彦の亜流としか思えないような感じなので僕はちょっと納得できないのですが、百人一首の謎があるおかげで全体としては楽しめました。とくに、主人公による歴史の解説が面白いです。セリフと地の文の区別がつかなくなるほど、どこまでも延々と続いていくのだけど、平安貴族のドロドロした闘いを分かりやすく説明してくれて、読まされます。
第9回メフィスト賞受賞作品。
自森人読書 QED―百人一首の呪
楡の木のそばに、ハワーズ・エンドはあります。綴られているのは、シュレーゲル家とウィルコックス家に関する物語。シュレーゲル家の姉マーガレットと妹ヘレンは知的で芸術を愛し、社会運動にも積極的に参加します。しかし、対照的な部分もあります。マーガレットはよく考えて行動し、一方ヘレンは自由奔放なのです。あるとき、ヘレンはハワーズ・エンドに招待されます。そして、ウイルコックス家の次男ポールと惹きあいますが、それは過ちということで処理されました。しかし、その後、ウイルコックス家がシュレーゲル家のそばに引っ越してきたことから、再び付き合いが始まり・・・
イギリスの小説。
長大な物語。冒頭には、「ただ結びつけることができれば・・・」と綴られています。多くのことが起こります。しかし、劇的な台詞はあまりないし、大袈裟な事件が起こることもありません。ゆらゆらしている海みたいです。
とはいえ、ドラマにはなっているので、流れに沿って進んでいけば暇ではありません。
翻訳者は吉田健一。流れるようで、引っかかる文体はみごとだと感じます。あっさりとしているので、すらすらと読めてしまいますが要約するのは難しいです。
E・M・フォースターは同性を愛していたそうですが、高踏的、あるいは貴族的ともいうべき態度と同性愛は結びつきやすいものなのかなぁ。なんというか奇怪です。
人と人がわかりあうことは可能なのかと問うているようです。しかし、答えは容易には見つかりません。向上心に溢れるレオナード・バストが憐れです。彼は労働階級だったがために、決して上へいくことができません。ラストは、なんというか、どうなんだろう。
読んだ本
E・M・フォースター『ハワーズ・エンド』
読んでいる最中
ジョン・バース『キマイラ』
少年は生まれたとき唇を閉じていましたが医師は強引にひらき、唇に脛の皮膚を移植します。すると、唇に産毛が生えてきます。寡黙な彼の友人は、デパートの屋上で生きた象インディラと、壁の隙間に挟まってしまった女の子ミイラだけでした。しかし、壊れたバスの中で生活している巨漢のマスターにチェスを習い、チェス盤の下でチェスをするようになります。そして、「盤下の詩人」リトル・アリョーヒンといわれるようになり・・・
チェスを扱った小説。
ぐいと心を掴む気持ち悪さとそれを包み込むような温かさが同居しています。唐突に襲い掛かってくる死が印象的です。痛々しい死が物語を動かしていきます。
海のように深くて広いチェスの世界を描き出す詩のような文体が楽しいです。
凄いものを持っているのだけど、社会には巧く適応していけない人ばかりが登場します。主人公の少年にしろ、マスターにしろ、ミイラにしろ、老人ホームの人たちにしろ、どこか変です。しかし、だからといって排除されることはなく、社会のはずれというか、深みで生きています。ポール・オースター作品のよう。
少し変な部分があろうとも矯正せずに、温かく見守ってくれる心の広い人たちが、主人公の周囲にはいます。彼らは、変な部分を見過ごすわけではありません。むしろ直視して、真摯に向き合おうとします。それが良いです。小川洋子の作品だということを強く感じます。
本屋大賞候補作。
読んだ本
小川洋子『猫を抱いて象と泳ぐ』
読んでいる最中
E・M・フォースター『ハワーズ・エンド』
『パルタイ』は倉橋由美子の短編集。『パルタイ』『非人』『貝のなか』『蛇』『密告』『後記』収録。
『パルタイ』
わたしは恋人から党に参加しないかと誘われます。しかし、そのためには経歴書が必要だといわれ・・・ 観念的な左翼と学生運動を扱った/諷刺した作品。
『非人』
ぼくは、「有能な集金人ではない」と雑役夫にいわれてしまいます。寮財政の赤字を気にしているのですが・・・
『貝のなか』
わたしはねっとりとした寮の中で生活しています。わたしは革命党に入らないかと誘われるのですが・・・
『蛇』
Kは7メートルの蛇を飲み込んでしまいます。尻尾は切り落としたのですが・・・
『密告』
ぼくは、Pと友達でした。しかし、Qが割り込んできます。
カフカを意識していることがよくわかります。しかし、倉橋由美子は、決してカフカではないし、むしろ筋が通っています。明晰なのです。人があわさることで生まれる組織というものの温みというか、気持ち悪さが、すっきりと示されています。
今の文学の先祖のようなものではないか。
新潮社。
読んだ本
倉橋由美子『パルタイ』
読んでいる最中
小川洋子『猫を抱いて象と泳ぐ』
物語の舞台は、ロートレックの絵が各所に飾られている別荘。二発の銃声が響き渡り、美女が次々と射殺されていきます。いったい、誰が犯人なのか。侵入者なのか。それとも内部の者なのか・・・?
ミステリ小説。
文章と会話が、妙にギクシャクしていて分かりにくいのですが、それは叙述トリックが仕掛けられているからです。最後に驚かされることになります。
映像化不可能と謳われていますが、確かにその通りだなぁと感じました。愉快です。とはいえ、前代未聞ではないし、それに、もっと後に書かれた『ハサミ男』などの方が洗練されていて、練られていてしかも派手です。まぁ『ロートレック荘事件』の方が先なのだからしかたないのかも知れないけど。
作中の人物にはあまり魅力が感じられないけど、まぁ駒みたいなものだからしかたないのかなぁ、とは思いますが、やはりそこはつまりらないです。
ロートレックという画家の存在が巧みに活かされていて凄いです。それもしっかりと伏線として物語の中に組み込まれています。
何でも書くことができてしまう筒井康隆という人には感心します。
読んだ本
筒井康隆『ロートレック荘事件』
読んでいる最中
ジョン・ファウルズ『魔術師 上』
森見登美彦の連作短編集。『きつねのはなし』『果実の中の龍』『魔』『水神』収録。
『きつねのはなし』
主人公は、古道具屋「芳蓮堂」で働いています。主人・ナツメさんから届け物を託され、着流し姿で生気のない無精髭の男・天城をたずねます。天城は、ぞっとさせられる非常に不気味な男なのですが・・・
『果実の中の龍』
大学一回生の時、ある研究会で先輩と知り合います。先輩は下宿にある図書室にいれてくれるのですが、半年後に去っていきます。去り際に黒革のノートと、彼女が古道具屋の「芳蓮堂」で買って先輩にプレゼントした〈龍の根付け〉を僕に送ってくれるのですが・・・
『魔』
私は家庭教師のバイトを先輩から引き継ぎ、西田酒店へいきます。そして、そこで直也・修二兄弟に出会います。彼らは、剣道好きの秋月や、部道具屋の娘・夏尾らと友達でした。ある日のこと、通り魔事件が起きます。ケモノが現れたのか。
『水神』
祖父の通夜が終わり、父、伯父二人、私は祖父の前で酒宴を開きます。彼らは様々なことを思い出していくのですが、そこには、いつも水が絡んでいて・・・
幻想小説。
これまで、鬱憤を抱え込んだダメな大学生を描いてきた森見登美彦が、『きつねのはなし』では幽玄な世界を描いています。端正な文体と朧な恐怖が良いです。なんとなく、内田百間を連想します。森見登美彦は凄い、と感じます。
謎が明かされることはないのですが、そこが良いです。日本のマジックリアリズムという言葉がぴったりではないか。
読んだ本
森見登美彦『きつねのはなし』
読んでいる最中
ジョン・ファウルズ『魔術師 上』
物語の語り手オブフレッドは侍女です。彼女は、司令官の子供を産むためだけに存在しています。つまり「2本足を持った子宮」なのです。オブフレッドは、かつての自由な生活は忘れられないのですが夫を失い、娘を奪われ、施設に収容されます。そして、女は子供を産まねばならないと刷り込まれ、司令官のもとへ送り込まれます。彼女は、司令官の妻がいるところで、司令官と愛のないセックスをするのですが・・・
ディストピア小説。
原理主義的なキリスト教徒が社会を支配しているようです。全てが監視されています、侍女たちはそもそも名前を与えられていないし、私物を持つこともできません。愛は禁じられています。逆らえば処刑されます。
非常に不気味な世界が描かれています。荒唐無稽に感じられますが、ありえるかも知れません。「健康と人類全体の利益のため」に、個人が犠牲にされる社会は怖い気がします。持ち出される理由が絶対的なまでに正しいからこそ、かえって危ないのではないか。
権力が都合良くつくりだした差別というものは、日常に潜んでいて意識できないからこそ怖いのではないか、と感じます。それが巧みに描かれています。
しかし、『侍女の物語』という小説は、ファシズムを非難して、単純に今の自由な社会を肯定している、というわけでもありません。様々な矛盾が溢れていることも直視しています。それが良いです。
カナダ総督文学賞、アーサー・C・クラーク賞受賞作。
読んだ本
マーガレット・アトウッド『侍女の物語』
読んでいる最中
森見登美彦『きつねのはなし』
西方大陸の神聖レヴァーム皇国と東方大陸の帝政天ツ上は争っています。天ツ上領内にあるレヴァーム自治区サン・マルティリアは天ツ上に圧力を受け、自治が危うい状況にありました。サン・マルティリアに暮らしている許婚ファナ・デル・モラルを救うため、レヴァーム皇国皇子カルロ・レヴァームは軍隊を派遣しますが、全滅。そのため、貧民でありながら優秀な戦闘機乗りである狩乃シャルルは、ファナをレヴァーム皇国に届けるよう頼まれます・・・
ファンタジー小説。
日本語が拙いです。架空の世界が構築されているところはみごとだし、それなりに面白いけど、それだっていかにも頭の中で組み立てたとしか思えないゲーム的な世界。しかも、それらが全て「可愛いお姫様と何日間も二人きり」という環境を生み出すためだけにつくられた言い訳になっているところは愉快です。
ありきたりな世界観や、戦争や、戦闘機は、二人を二人だけにするため、あるいは二人の甘酸っぱい恋を盛り上げるための道具に過ぎないわけです。ゴテゴテしているのに、どうしてこんなに薄っぺらいのだろう。
しかも、恋愛の描き方まで陳腐だから、読みどころがない・・・ 幼い頃、最下級のシャルルとお姫様のファナは出会い、鬼ごっこしていたのだそうですが、もうその時点でご都合主義的ではないか。というか、もうツッコミどころが満載。
キャラクターは非常に陳腐。描写はいちいち型にはまっていて、もう読みすすめていく気がうせてきます。最初から、ラストが想像できてしまうのです。
ラノベ以外の何物でもないので読んでいてうんざりでした。という書き方はよくないかも知れないけど、やっぱり、ラノベというものは1冊読めば他作品は読まなくても、あらすじが類推できてしまうようなものに過ぎない気がしてきます。
小学館。
読んだ本
犬村小六『とある飛空士への追憶』
読んでいる最中
マーガレット・アトウッド『侍女の物語』
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
ブログ内検索
最新記事
(01/04)
(02/17)
(02/16)
(09/29)
(08/06)
(08/05)
(08/05)
(08/05)
(08/05)
(08/04)
最新TB
最古記事
(08/08)
(08/08)
(08/09)
(08/09)
(08/10)
(08/11)
(08/12)
(08/12)
(08/13)
(08/13)
アクセス解析
